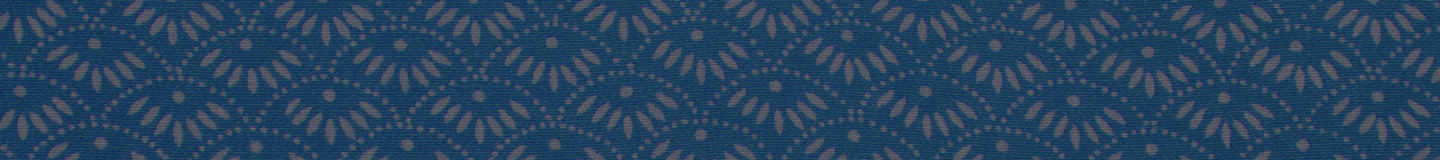GX2040ビジョンを閣議決定
GX2040ビジョンが閣議決定され、日本の脱炭素社会への移行がさらに加速している。政府は2023年12月にGX推進戦略を策定し、2025年2月には第7次エネルギー基本計画とGX2040ビジョンを決定した。この戦略は、エネルギー供給の構造転換と産業の脱炭素化を目的としており、再生可能エネルギーの普及や水素・アンモニア燃料の活用が進められている。
製造業においては、工業炉の電化や省エネ設備への投資が加速し、鉄鋼業や素材産業では水素・アンモニア燃料の導入による脱炭素化が検討されている。自動車産業では電動化とライフサイクルアセスメント(LCA)の導入が進み、サプライチェーン全体でのグリーン化が推進されている。資源循環の強化も重要であり、鉄・アルミスクラップのリサイクル技術の向上やAI技術を活用した鉄スクラップの自動判定システムの導入が進められている。
中小企業に求められるGX対応
日本では、企業や事業者が二酸化炭素(CO₂)の排出量を公表する取り組みが進められている。環境省の温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度によって、一定規模以上の事業者は自社の排出量を算定し、国に報告することが義務付けられている。この制度は、企業の排出量を可視化し、削減努力を促すことを目的としている。
また、2050年のカーボンニュートラル達成に向けて、企業が自主的に排出量を公表する動きも広がっている。とくに、大手企業はサプライチェーン全体の排出量を把握し、取引先と協力して削減目標を設定するケースが増えている。中小企業にとっては、GX推進の一環として排出量の公表が求められる場合があるが、報告の負担を軽減するため、すべての事業者からの報告情報については、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度 フロン類算定漏えい量報告・公表制度ウェブサイトにて公表されている。
中小企業の脱炭素経営は、今後ますます重要な課題となる。日本の中小企業は全体の99.7%を占めるが、温室効果ガス排出量は全体の1~2割程度である。そのため、大企業と比べて排出量は少ないものの、GX推進の流れの中で脱炭素化への対応が求められている。
現在、多くの中小企業が省エネ設備の導入や再生可能エネルギーの活用を進めている。例えば、LED照明や高効率空調システムの導入、太陽光発電の設置などが一般的な取り組みである。また、カーボンフットプリント(CFP)の算定を行い、取引先との連携を強化することで、サプライチェーン全体での脱炭素化を進める動きも見られる。
一方で、脱炭素経営の推進には課題もある。とくに、資金やノウハウの不足が大きな障壁となっており、約56.5%の企業が「マンパワー・ノウハウが不足している」と回答している。また、排出量の具体的な算定方法が分からない企業も多く、政府や自治体による支援策の活用が不可欠となる。
今後の展望としては、GX経済移行債や補助金を活用した設備投資の促進、専門家によるアドバイスの提供、環境認証の取得などが進むと考えられる。脱炭素経営の推進は、コスト削減や市場競争力の向上につながるため、中小企業にとって経営戦略の重要な要素となる。
環境に配慮した経営を行うことで、企業イメージの向上が期待される。取引先や消費者からの評価が高まり、競争力の強化につながるほか、環境意識の高い企業との取引が増えることで新たな市場機会の獲得につながるだろう。
さらに、人材確保と社員のモチベーション向上の面でもメリットがある。環境に配慮した企業は、若い世代の求職者からの関心が高く、採用活動において有利に働く。また、社員の意識が向上することで、企業全体の生産性向上が期待できる。
GXは、日本の産業競争力を維持しながら環境負荷を軽減する重要な施策であり、今後さらに発展することが期待される。政府、産業界、市民が協力しながら持続可能な社会の構築を目指すことが求められている。