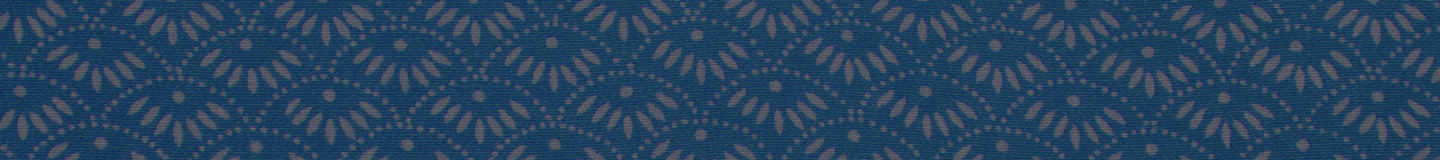CASE・EV・国内生産体制から読み解く構造転換の本質
日本の自動車産業は、長年にわたり製造業の中核を担い、経済・雇用・技術の面で国の成長を支えてきたが、いま「100年に一度の変革期」と称される構造的転換点に直面している。技術革新、社会的価値観の変容、国際競争の激化が複合的に作用し、従来のビジネスモデルや産業構造に再定義が迫られている。
自動車産業は、単なる車両製造にとどまらず、素材供給からサービス提供までを包含する総合産業である。その裾野の広さは、鉄鋼・ゴム・電子部品などの素材産業から、販売・整備・保険・交通インフラに至るまで、経済・社会構造に深く根を張っている。
最新の統計によると、日本の製造品出荷額は約361兆円であり、そのうち自動車産業は約63兆円を占める。これは全製造業の17%以上を占める規模を維持している。すなわち、自動車産業は日本の製造業を支える中核的存在として、現在もその影響力と重要性を維持している。
しかし近年、自動車産業は「大量生産・大量消費」型の従来モデルからの転換を余儀なくされている。その背景には、技術革新の加速と社会的価値観の変化が複合的に作用している。なかでも「CASE(Connected, Autonomous, Shared & Services, Electric)」と呼ばれる潮流は、自動車の概念そのものを再定義し、産業構造の根本的な見直しを促している。
CASEは、車両のインターネット接続(Connected)、自動運転技術の進化(Autonomous)、所有から利用への転換(Shared & Services)、そして環境負荷低減を目的とした電動化(Electric)を指す。これらは単なる技術革新にとどまらず、産業構造やビジネスモデルの根本的な再設計を促すものであり、国内メーカーもCASEを軸に戦略転換を加速させている。
今後、CASEの進化は「MaaS(Mobility as a Service)」という交通全体を統合するサービスモデルへと発展し、社会全体の移動のあり方を大きく変える可能性を秘めている。
トヨタの「300万台体制」が守るものづくりの根幹
2024年、日本国内の総生産台数は約823万台と前年比8.5%減となり、2年ぶりのマイナス成長となった。ダイハツ工業の認証不正問題による生産停止や、海外市場の需要鈍化が主因である。とくにトラックの生産は11.8%減と大幅に落ち込み、商用車分野における供給制約が顕著となった。
一方、海外生産は約1,648万台で前年比5.9%減。国内外合計では約2,471万台となり、海外生産が国内の約2倍に達している。これは日系メーカーのグローバル展開の強さを示す一方で、国内生産の戦略的意義を再認識させる結果でもある。
トヨタは「国内生産300万台体制」という定量的かつ戦略的な目標を明言しており、これは日本の自動車産業における単なる生産目標ではなく、産業構造・雇用・技術継承を支える戦略的基盤である。
トヨタはこの体制を「石にかじりついてでも守る」と明言し、2024年度には国内で約323万台を生産。国内乗用車メーカー8社の総生産台数の約4割を占める規模である。
この体制の維持は、約550万人が従事する自動車関連産業の雇用を守ることに直結しており、企業利益を超えた社会的責任と捉えられている。仮に国内生産が半減すれば、サプライチェーン全体に波及し、数十万人規模の雇用喪失につながる可能性がある。
また、国内生産は高度な技能や要素技術の蓄積、改善文化の継承、新技術の実証・展開の場として、グローバル展開における「マザー工場」の役割を担っている。設備の老朽化や人手不足といった課題に対応するため、トヨタは2030年をめどに東海地方から東北・九州への一部移管を進めており、生産性向上と地域分散の両立を図っていく方針だ。
ホンダは国内生産台数が約80万台で、鈴鹿・埼玉などに拠点を構える。一方、海外生産比率が高く、グローバル展開を重視している。日産は国内生産台数が約50万台で、九州・栃木などに拠点を持つが、こちらもグローバル展開を重視している。
日本メーカーのハイブリッド車(HEV)中心の全方位戦略
グローバル市場では、EVシフトに対する揺り戻しの兆候が顕著だ。欧州ではEV補助金の縮小や内燃機関車の販売禁止方針の見直しが進み、米国ではEV在庫が過去最高水準に達するなど、消費者の購買志向と充電インフラの整備状況との間に乖離が生じている。
こうした中、日本の自動車メーカーは、HEVを中心とした全方位戦略により、相対的な競争力を維持している。EV一辺倒ではなく、内燃機関・ハイブリッド・電動化のバランスを取ることで、政策変更や市場の不確実性に柔軟に対応している点が評価されつつある。
2024年度の国内新車販売台数(登録車+軽自動車)は約457万台となり、3年連続で前年を上回った。軽自動車市場ではホンダ「N-BOX」やスズキ「スペーシア」が好調を維持し、普通乗用車市場ではトヨタが圧倒的なシェアを誇った。ハイブリッド技術を核とした環境対応車のラインナップが、消費者の支持を集めている。
日本の自動車産業は、CASEやEVといった技術潮流に加え、地政学的リスクや政策変動といった外部環境の揺らぎに直面しながらも、国内生産体制の堅持を通じて、雇用・技術・経済基盤の維持に努めている。トヨタ自動車が2026年3月期に世界生産台数1000万台を計画し、米国の高関税という逆風下でも国内生産300万台体制を維持する姿勢は、その象徴的な取り組みである。
今後、自動車産業が持続可能性と競争力を両立させるためには、技術革新に加え、政策・人材・地域との連携を含めた多層的な戦略が求められる。CASEやMaaSの進展が社会の移動のあり方を根本から変える中で、日本の自動車産業は「製造業の枠」を超えた社会的価値創造の担い手として、次なる100年の礎を築くことが期待されている。