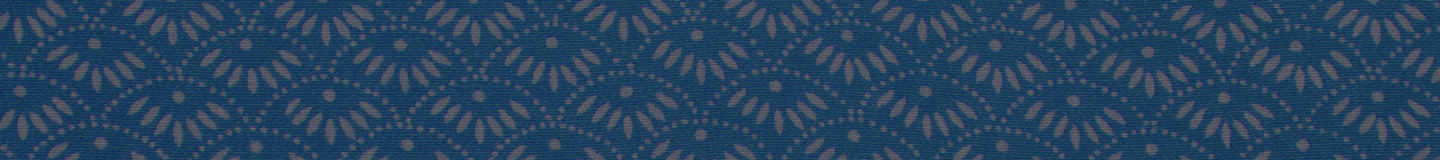近年、気候変動の影響がますます顕著になっている。異常気象や海面上昇、氷河の融解などが自然環境に深刻な影響を与えている現実を目の当たりにする。
気候変動の主な原因は、人間活動による温室効果ガスの排出である。温室効果ガスは、地球の大気中に存在し、太陽からの熱を保持する役割を持つ気体のことだ。地表から放射される熱を吸収し、その熱を再び地表へ戻すことで大気を暖める役割を果たしている。このプロセスが「温室効果」と呼ばれる。ただし、過剰な排出が続くと地球温暖化が進行し、極端な気候変動や海面上昇などの深刻な影響を引き起こす。
温室効果ガスの発生要因には化石燃料の燃焼、森林破壊、農業活動などが挙げられ、これらが地球の平均気温の上昇や気象パターンの変化を引き起こしているとされる。2024年の世界平均気温は、産業革命前の水準より約1.55度上昇し、観測史上最高を記録した。各地で干ばつや洪水などの極端な気象現象も増加している。
気温の上昇は、さまざまな問題を引き起こす。その一例として、北大西洋と北極海の間に位置する世界最大の島、グリーンランドを挙げる。面積約216万平方キロメートルのグリーンランドは、島全体の約80%が氷に覆われている。しかし、気温の上昇により陸上の氷床や氷河が融解し、新たに海に流れ込む水が増加することで、海面上昇を引き起こしている。
海面上昇は地球規模で深刻な影響を及ぼす。陸地の減少により、南太平洋地域に位置するツバルやモルディブなどの島国では水没の危険が高まり、環境難民の増加が懸念される。水害の増加により、高潮や洪水が頻発し、沿岸地域の住宅やインフラが壊滅的な被害を受けることがある。さらに、海水が河川や地下水に逆流する結果、飲料水が塩水化し、安全な水の供給も難しくなる。
国内に目を向けると、地球温暖化が魚の生息範囲に大きな変化をもたらしている。従来は九州や四国など西日本沿岸で多く見られたサバ(鯖)や、関西地方及び北陸地方(とくに富山湾)で多く漁獲されていたブリ(鰤)が、海水温の上昇に伴い東北地方や北海道周辺でも大量に捕れるようになった。北海道では『寒ブリ』が地域特産品として注目されている。一方で、サンマ(秋刀魚)やホッケは、従来は北海道や三陸沖での漁獲が主だったが、北太平洋の水温上昇の影響で日本近海への回遊量が減少し、漁獲量が大幅に低下している。
気候変動対策の国際的な取り組みとして、2015年に採択されたパリ協定がある。この協定は、産業革命以前と比較して地球の平均気温上昇を2℃未満に抑え、さらに1.5℃を目指す努力を各国に求めている。また、各国は国連気候変動枠組条約 (UNFCCC) に基づき、温室効果ガス削減目標(NDC)を提出し、その進捗を定期的に報告している。
わが国は、2050年までに温室効果ガスの排出を実質ゼロにする「カーボンニュートラル」の達成を目標としている。個人の日常生活や消費行動、社会的な活動を通じて、この目標への貢献が可能である。
GX(グリーントランスフォーメーション)政策においては、経済成長と脱炭素化の同時実現を追求している。この政策は再生可能エネルギーの導入や省エネ技術の普及を推進するものであり、脱炭素技術や再生可能エネルギーへの投資が増加している。また、炭素税や排出量取引制度などカーボンプライシングを導入することで温室効果ガス排出削減を促進している。
一方で、地球温暖化は特定の条件下で一部の地域や活動に恩恵をもたらす場合もある。温暖化により寒冷地の気温が上昇し、農業が可能となる地域が広がることが予想される。例えば、カナダでは、これまで農作物の栽培が困難だった地域で農業が拡大する余地がある。また、北極海の氷が減少することで新たな海運航路が開かれ、貿易効率の向上が期待される。ただし、これらの恩恵は温暖化がもたらす損害を補うほどのものではなく、気候変動の影響を評価する際には悪影響を重視すべきである。