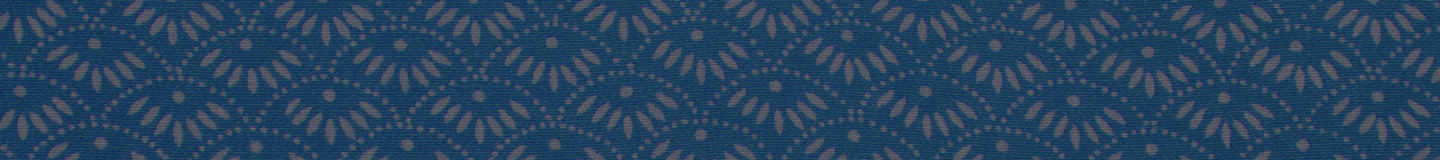日本の消費市場では物価上昇が続いている。円安、資源価格の高騰、物流費の上昇など、外的要因が重なり、生活必需品から耐久消費財まで幅広い分野で値上げが相次いでいる。一方で、賃金の伸びは限定的で、実質的な購買力は回復していない。こうした状況下では、インフレの「質」を見極めることが重要な課題となっている。
ヒット商品から読み解くインフレの二つの顔
インフレーションには主に「ディマンドプル型(需要主導型)」と「コストプッシュ型(供給制約型)」の二つがある。前者は景気回復や所得増加によって需要が供給能力を上回り、物価が上昇する現象であり、後者は原材料費や人件費、エネルギー価格などの供給側のコスト上昇によって企業が価格を引き上げざるを得ない構造的なインフレである。
たとえば、ある新型スマートフォンが発売され、SNSで話題となり、全国の店舗に長蛇の列ができた。消費者の購買意欲は高く、「高くても欲しい」という心理が働き、メーカーは価格を引き上げても需要は衰えない。これはディマンドプル型インフレの典型である。一方、同じスマートフォンでも、半導体不足や原材料の高騰、円安による輸入コストの上昇などが重なれば、企業は利益を維持するために価格を引き上げざるを得ない。これはコストプッシュ型インフレである。
2025年1〜3月期の名目個人消費は過去最高を更新したが、物価上昇が賃金の伸びを上回っているため、実質個人消費は依然としてコロナ禍前の水準に届いていない。内閣府の「消費動向調査」によれば、2025年7月の消費者態度指数は33.7と前月から低下し、「暮らし向き」「収入の増え方」「雇用環境」などの意識指標も軒並み悪化している。物価上昇が家計と企業の双方に影響を及ぼす中で、政府の役割はますます重要になっている。とくにコストプッシュ型インフレが中心となる局面では、生活者の購買力を支える財政政策と、供給制約を緩和する産業政策の両面からの対応が求められる。
家計支援としては、定額減税やエネルギー補助金、子育て世帯への給付などを通じて可処分所得の底上げが図られている。ただし、こうした一時的な措置だけでは限界があり、所得税や社会保険料の構造的な見直しによる持続的な購買力の確保が課題となっている。大手企業はブランド力や市場支配力があるため、値上げしても顧客離れが起きにくく、価格転嫁が比較的容易である。現在は総合電機や自動車、食品大手などは原材料高騰を乗り越え、むしろ過去最高益を更新している企業もある。値上げによって利益を確保し、賃上げや設備投資に回す好循環が生まれている。
一方で、中小企業は価格転嫁が難しく、原材料やエネルギーコストの上昇を吸収せざるを得ないケースが多い。取引先との力関係や顧客の価格感度が高いため、値上げすれば受注が減るリスクがある。中小企業にとって、価格転嫁は「選択肢」ではなく「生存戦略」に近い。原材料費やエネルギーコスト、人件費の上昇が続く中、価格を据え置いたままでは利益が圧迫され、事業継続そのものが危うくなる。帝国データバンクの調査では、2025年時点で中小企業の約4割が「コスト上昇分を価格に反映できていない」と回答しており、利益率の低下や資金繰りの悪化が深刻化している。価格転嫁ができない企業ほど、賃上げや設備投資にも踏み切れず、結果として競争力の低下を招くという悪循環に陥っている。
政府には、こうした中小企業の価格転嫁を後押しする環境整備が求められる。下請け取引の適正化、公正な価格交渉の支援、原材料高騰への補助金、資金繰り支援、デジタル化・省力化投資への助成などが重要である。また、消費者にも「安さだけを求める」意識から、「価値に見合った価格を受け入れる」姿勢への転換が求められる。
金融政策と財政政策の協調が問われる局面
金融政策との連携は、現在の日本経済において欠かせない要素である。日本銀行は段階的な利上げを進めている。これは、持続的な物価上昇に対して金融引き締めを通じてインフレ期待を抑制する狙いがある。だが、現在の物価上昇の主因は、需要の過熱ではなく、原材料費やエネルギー価格の高騰、物流の混乱などによる供給制約にある。いわゆるコストプッシュ型インフレであり、金利政策だけでは十分な効果が得られないのが実情だ。それでも利上げが検討されるのは、インフレ期待の抑制や通貨防衛といった目的がある。物価が上がり続けると、企業や消費者の間に「今後も値上がりが続く」という心理が広がり、先回りした値上げや賃上げ要求が連鎖的に起こる。利上げはこうした期待の暴走を抑える効果がある。また、金利の上昇は円安の是正にもつながり、輸入物価の抑制を通じて間接的にインフレ圧力を緩和する役割も果たす。
一方で、利上げには副作用もある。企業の投資意欲や家計の消費が冷え込み、景気の減速を招く可能性がある。とくに中小企業や住宅ローンを抱える世帯にとっては、資金繰りや生活費の負担が増すことになりかねない。さらに、設備投資の停滞は供給力の強化を遅らせ、インフレの根本原因である供給制約の解消を妨げるリスクもある。だからこそ、金融政策と財政政策の協調が不可欠となる。日本銀行がインフレ期待を抑えるために利上げを進める一方で、政府は財政面から景気の急激な冷却を防ぎ、生活者と企業の足元を支える役割を担う必要がある。定額減税や給付金による家計支援、原材料高騰への補助金や設備投資への助成などを通じて、購買力と供給力の両面を支える政策が求められる。
このように、コストプッシュ型インフレという複雑な課題に対しては、単独の政策ではなく、複合的かつ協調的な対応が必要である。政府と日本銀行がそれぞれの政策手段を駆使しながら、目的を共有し、タイミングを調整し、国民や市場に対して一貫した方針を示すことが、マクロ経済の安定に不可欠である。インフレは単なる価格の上昇ではなく、経済の構造と生活の質に深く関わる現象である。その背景を見極め、企業・政府・消費者がそれぞれの立場から責任ある行動を取ることで、物価上昇を「危機」ではなく「転機」として乗り越える道が開ける。今こそ、社会全体でインフレの本質に向き合う時である。