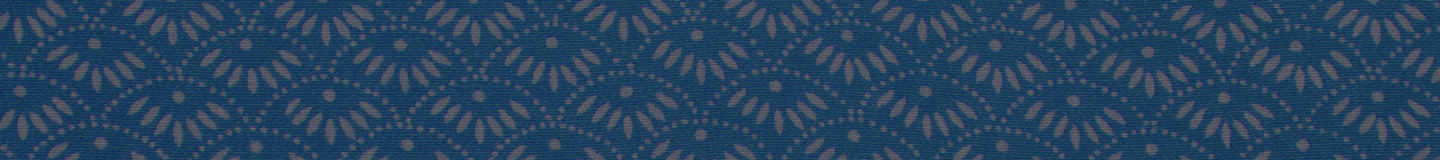近年、日本人の人口減少が加速しており、社会全体に深刻な影響を及ぼし始めている。2025年時点の総人口は約1億2,065万人であり、前年から約90万人の減少が記録された。これは統計開始以来最大の減少幅であり、少子高齢化と出生数の減少による自然減の拡大が主因である。
出生数は約68万人で過去最少を更新し、死亡数は約160万人で過去最多となった。厚生労働省の人口動態統計によれば、死亡数の増加は主に高齢化の進行によるものであり、死因の傾向にもその影響が色濃く表れている。
死因の最多は悪性新生物(がん)で約38万人、次いで心疾患(高血圧性を除く)が約21万人、老衰が約16万人である。老衰による死亡者数は年々増加しており、平均寿命の延伸とともに自然死の割合が高まっていることがうかがえる。また、自殺による死亡は約2万人であり、若年層を中心に依然として深刻な社会課題となっている。 結果として、自然減は91万人を超え、人口構造の歪みが一層顕著となっている。とくに地方では高齢化が深刻化しており、地域社会の持続可能性が強く問われている。
一方で、外国人住民の増加が目立っており、2025年には約368万人に達し、前年比で10%以上の増加となった。これは過去最多となる水準であり、東京都以外の地域で日本人の人口が減少する中、外国人の増加が一部地域の人口維持に大きく寄与している。
この増加の背景には、労働力不足を補うための制度改革や、留学・定住を促進する政策の影響があると考えられる。在留資格別に見ると、永住者が約90万人と最も多く、長期的に日本に定住する外国人が増加していることが分かる。次いで、技能実習(約42万人)や技術・人文知識・国際業務(約39万人)など、労働目的での滞在者が多くを占めている。
また、留学生は約37万人に達し、日本の教育機関における国際化が進んでいることを示している。近年急増しているのが特定技能(約25万人)で、介護・外食・建設などの分野で即戦力として期待されており、地方都市でもその存在感が高まっている。
このような外国人住民の増加は、地域経済や文化の多様性に新たな活力をもたらす一方で、言語・生活支援・教育などの面での受け入れ体制の整備が求められている。今後、日本社会が多文化共生をどのように実現していくかが、重要な課題となるだろう。
今後、外国人が日本の人口の10%以上を占める可能性も指摘されており、社会構造の変化が進行している。
若者が結婚・出産を選ばない理由
2025年の合計特殊出生率は1.15であり、晩婚化や非婚化が進行し、結婚を選択しない若者が増加している。加えて、経済的不安、育児支援の不足、長時間労働などが、子どもを持つことへの心理的・物理的な障壁となっている。
一方、高齢化の進行により死亡数が増加している。医療の進歩により平均寿命は延びているものの、65歳以上の高齢者が全人口の約30%を占める現在、年間の死亡数は出生数を大きく上回っている。これにより自然減が拡大し、人口全体の縮小が加速している。
さらに、出産可能な年齢層の女性の減少も少子化の一因である。若年層の人口が減ることで、将来的な出生数の回復も困難となり、悪循環が生じている。人口減少の背景には、経済的不安、育児支援の不足、働き方の硬直性などがあり、若年層の結婚・出産への躊躇が顕著である。とくに女性に偏る育児・介護負担や、社会的支援の不十分さが課題として浮上している。
政府は保育の無償化や柔軟な勤務制度の導入など、少子化対策を進めているが、現時点では効果は限定的である。地方自治体では*関係人口の創出や外国人との共生に向けた取り組みが始まっており、今後の人口政策は多様性と持続可能性を軸に再構築される必要がある。
*関係人口(かんけいじんこう)とは、地域に「住んでいる人(定住人口)」でも「観光で訪れる人(交流人口)」でもない、その地域と継続的・多様な形で関わる人々のこと
持続可能な社会の構築に向けて
日本の人口は、戦後から2008年頃までは増加傾向にあったが、それ以降は減少へと転じている。この人口の変化には、それぞれ異なる社会的背景が存在する。
戦後の人口増加期には、まず1947年から1949年にかけて第1次ベビーブームが発生した。戦争の終結に伴い結婚・出産が急増し、出生数は年間270万人を超える水準に達した。その後、1950年代から1970年代にかけての高度経済成長期には、雇用の安定や所得の向上が進み、都市部への人口集中が加速した。
農村から都市への人口移動も活発となり、核家族化が進行した。住宅政策や教育制度の整備も相まって、安定した生活基盤が人口増加を支える要因となった。1971年から1974年には第2次ベビーブームが起こり、再び出生数が増加した。
一方、2008年をピークに人口は減少へと転じ、現在は人口減少社会に突入している。この背景には、少子化と高齢化の進行がある。晩婚化や未婚率の上昇、経済的不安、育児負担の増加などが出生率の低下を招き、2005年には*合計特殊出生率が過去最低の1.26を記録した。また、団塊世代の高齢化により医療・介護の需要が急増し、社会保障制度への負担が深刻化している。
*合計特殊出生率(TFR:Total Fertility Rate)とは、1人の女性が一生の間に産むと想定される子どもの平均数を示す人口統計の指標のこと。これは、15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計して算出される。
さらに、都市部への人口集中が続く一方で、地方では若年層の流出と出生数の減少が進み、地域の存続が危ぶまれる自治体も現れている。こうした状況は、労働力人口の減少、国内市場の縮小、生産性の低下など、経済全体にも影響を及ぼしている。
今後は、育児支援の充実、働き方改革、外国人材の受け入れなど、多面的な対策が求められる。人口の変化は社会の構造そのものに影響を与えるため、長期的な視点に立った取り組みが不可欠である。
少子化対策の強化においては、若い世代が安心して結婚・出産・子育てできる環境の整備が不可欠である。具体的には、保育施設の拡充、待機児童の解消、育児休業制度の充実、経済的支援の強化などが求められる。また、働き方改革を推進し、男女ともに育児と仕事を両立できる柔軟な勤務制度の導入も重要である。
外国人材の受け入れと定着支援も、人口減少対策の重要な柱の一つである。労働力不足を補うために、技能実習制度や特定技能制度を活用し、外国人が安心して働き、暮らせる環境を整える必要がある。言語教育、生活支援、地域との交流促進など、多文化共生の視点を持った施策が不可欠である。
加えて、高齢者の活躍支援も重要である。定年後も働ける環境の整備や、地域活動への参加を促進することで、高齢者の知見や経験を社会に活かすことが可能となる。
人口減少は避けがたい現象であるが、その向き合い方次第で社会の未来は大きく変化する。持続可能な社会を築くためには、出生率の回復に加え、地域の再生、働き方の見直し、多様な人材の活用など、複合的かつ長期的な視点に立ったアプローチが求められる。