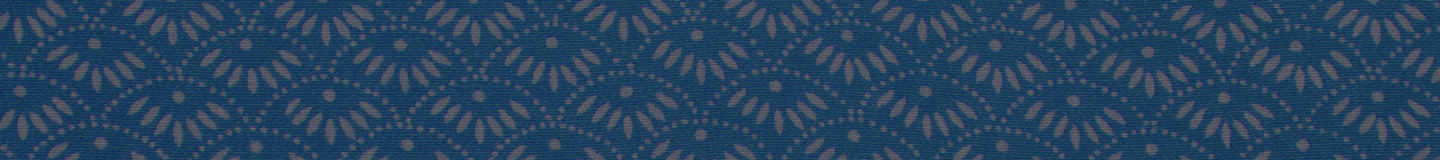日本社会は現在、少子高齢化、環境問題、教育格差、貧困など、複雑に絡み合った多くの課題に直面しています。これらの問題は、私たちの暮らしだけでなく、経済や地域社会の持続可能性にも深く関わっており、社会全体での取り組みが求められています。
たとえば、子どもの貧困や*ヤングケアラーの増加は、教育機会の不平等や将来の選択肢の狭まりにつながっています。家庭の経済状況によって進学や学習の機会が制限されることで、貧困の連鎖が生まれるリスクも高まります。
一方、地方では人口減少と高齢化が進み、過疎化や*限界集落の増加によって、交通、医療、教育などの社会インフラの維持が困難になっています。若者の都市部への流出が続く中、地域の活力をどう維持するかが問われています。人口減少に伴い、病院や学校、バス路線などの利用者が減少し、採算が取れずに閉鎖・廃止されるケースが増えています。
国土交通省の推計では、2050年には病院の存在確率が50%以下になる市町村が、全国の約66%に達する見込みです。高齢者の割合が増えることで医療・介護の需要は高まる一方、提供する人材が不足しており、とくに中山間地域では住民の半数以上が高齢者という限界集落が増加し、生活インフラの維持が一層困難になっています。
中小製造業が抱える構造的課題
こうした社会的な背景の中で、日本の中小製造業もまた、大きな転換期を迎えています。
日本国内には約385万社の企業が存在し、そのうち約99.7%を中小企業が占めており、日本経済の屋台骨として重要な役割を担っています。しかし現在、多くの企業が人材不足、技術継承の困難、デジタル化の遅れ、設備の老朽化といった複合的な課題に直面しています。とくに、熟練技術者の引退による技術の喪失や、若手人材の確保難は深刻であり、ものづくりの現場における持続可能性が強く問われています。
加えて、グローバル競争は激化の一途をたどっており、中小製造業への影響が深刻化しています。新興国の台頭により価格競争は一段と激しくなり、差別化の困難さも重なって、海外企業との競争もますます熾烈さを増しています。さらに、原材料や部品の調達リスク、資金調達の困難さ、販路開拓の遅れなども、事業継続における大きな障壁となっています。
医療やエネルギー分野と同様に、環境対応や脱炭素への社会的要請も強まっており、省エネ設備や再生可能エネルギーの導入には多額の初期投資が必要となるため、対応に苦慮する企業も少なくありません。
取引慣行に関する課題も看過できない状況です。多くの中小製造業は下請け構造の中で価格決定権が弱く、原材料費や人件費の高騰を十分に価格へ転嫁できず、利益が圧迫されています。契約条件の不透明さや口頭契約、仕様変更によるトラブルも頻発しており、取引の公正性と透明性が問われています。
また、支払サイトの長期化によって資金繰りが悪化し、信用力の格差から新規取引の獲得にも苦戦を強いられています。取引先の海外移転や撤退により受注が突如途絶えるケースもあり、グローバルなサプライチェーンの変化に柔軟に対応する力が求められています。
しかも、電子契約や受発注システムの導入が進んでいない企業では、デジタル対応の遅れが取引先からの信頼低下や機会損失につながるリスクも高まっており、取引基盤の近代化は喫緊の課題です。
日本社会が持続可能な未来を築くためには、こうした複雑に絡み合う社会課題と経済課題の双方に目を向け、産業界・地域・行政が連携して解決に取り組む姿勢が不可欠です。制度改革と現場支援の両輪によって、包摂的かつ持続可能な社会の実現を目指すことが求められています。
用語解説
*ヤングケアラー:家族の介護や世話を日常的に担っている18歳未満の子どものことを言います。近年、日本でも社会問題として注目され、支援の必要性が高まっています。
*限界集落:住民の過半数が65歳以上の高齢者で構成されており、地域社会の維持が困難になっている集落を指します。