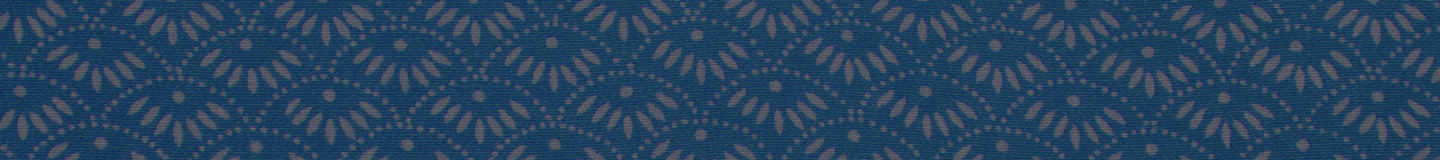近年、日本国内における外国人労働者の増加に伴い、不法滞在者の存在および偽造在留カードの流通が深刻な社会的課題として浮上している。両者は密接に関連しており、制度的な脆弱性と実務上のリスクを内包している。不法滞在の背景には、難民申請の不認定、技能実習制度からの失踪、在留資格の更新漏れなど、様々な事情が存在するが、いずれも法的には許容されない。2025年1月1日時点において、日本国内の不法滞在者数は74,863人と公表されており、前年から約5.4%減少したものの、依然として7万人台を維持している。
ピーク時である1993年には約30万人に達していたが、制度整備の進展により大幅に減少した。現在の不法滞在者の約61%は「短期滞在」からのオーバーステイによるものであり、退去強制処分が確定しているにもかかわらず滞在を続けている外国人は3,122人に上る。
政府は「不法滞在者ゼロプラン」を掲げ、電子渡航認証制度(JESTA)の導入や送還体制の強化など、複数の施策を推進している。国籍別の不法滞在者数では、ベトナムが最多の14,296人であり、次いでタイが11,337人、韓国が10,600人と続く。これらの傾向から、ベトナム、中国など技能実習制度との関連が深い国籍では制度上の課題や失踪事例が影響していると考えられる。一方、韓国やタイなどの国籍においては、観光目的で入国後に滞在を継続するオーバーステイが目立ち、短期滞在ビザ免除制度の悪用が課題となっている。
偽造在留カードは、本来の在留資格や滞在期間を偽装するために不正に作成されたものであり、外見上は本物と酷似していることが多い。そのため、企業や行政機関が表面的な確認のみを行った場合、真正性を見抜くことは困難である。こうした偽造カードは、在留期限が切れた外国人や、そもそも適法な在留資格を持たない者が摘発を免れ、就労や居住を継続するための手段として利用されている。
在留カードを売ることの危険性と社会的影響
在留カードは、日本に中長期滞在する外国人に対して交付される、極めて重要な公的身分証明書である。氏名、国籍、生年月日、在留資格、在留期間、就労の可否などの個人情報が記載されており、日本での生活において不可欠な存在だ。銀行口座の開設、住居の契約、就職活動、医療機関の受診など、日常のあらゆる場面で提示を求められることがある。
しかし近年、この在留カードが違法に売買される事例が報告されている。売買の背景には、経済的困窮や不法滞在者への便宜、さらには犯罪組織による偽造目的など、さまざまな事情が存在する。生活に困っている外国人が現金を得るためにカードを売るケースもあれば、在留資格を持たない者が他人のカードを使って働こうとするケースもある。また、犯罪グループが偽造カードを作成するために、実在するカードを買い取るという組織的な動きも確認されている。
実際の摘発事例として、2023年に兵庫県警と警視庁などの合同捜査本部が摘発した「偽造在留カード工場」が挙げられる。この事案では、千葉県旭市の民家が製造拠点として使用されており、パソコンやプリンター、ホログラム加工用のラミネートフィルムなどが押収された。現場からは約120枚の偽造カードとともに、約2万人分の顧客データが記録されたパソコンも発見されている。グループは中国籍の人物を中心に構成されており、SNSや中国の交流サイト「微信(WeChat)」を通じて注文を受け、1枚あたり1,500円から7,000円程度で販売していた。
販売先は主にベトナム、インドネシアなどの技能実習生や留学生であり、ブローカーを介して広範囲に流通していたとされる。摘発当時、約1億4,000万円の売上があったと見られており、国内最大規模の偽造組織と報道された。また、2025年には埼玉県の一軒家にて、中国籍の男性4名が不法残留容疑で摘発されている。この住宅は偽造在留カードの送付先として利用されており、強制調査により複数の偽造カードと関連機器が押収された。
信用力の高い身分証が闇市場で流通
最近では、健康保険証や運転免許証などの公的身分証明書が在留カードと「セット販売」されていた事例も複数確認されている。健康保険証が偽造される背景には、医療機関での受診や就労時の本人確認、さらには銀行口座開設など、在留カード単体では対応できない場面での補完的な身分証明としての需要があると考えられる。とくに、企業や行政機関が複数の身分証明書を求める場合、偽造カードの「セット販売」は不法滞在者にとって利便性が高く、摘発の難易度を高める要因となっている。
こうした偽造書類の流通は、単なる不法滞在の隠蔽にとどまらず、医療保険制度の悪用や金融犯罪への関与など、社会全体に広範なリスクをもたらすものである。現在、出入国在留管理庁はICチップ読取アプリの普及を進めているが、現場での確認体制や企業の意識向上も不可欠である。これらの事例は、偽造カードの流通が個人の違反にとどまらず、組織的かつ広域的に展開されていることを示している。制度の隙間を突いた滞在延長が可能となっている実態を浮き彫りにしている。
こうした行為は、単なる不正利用にとどまらず、社会全体に深刻な影響を及ぼす。偽造された在留カードが流通することで、不法就労や詐欺などの犯罪が助長されるほか、外国人に対する不信感が広がり、共生社会の実現を妨げる要因となる。もし「カードを売ってほしい」「貸してほしい」と言われた場合、それは犯罪に巻き込まれる危険信号である。
技能実習制度や特定技能制度、育成就労制度を活用して外国人を雇用している企業においては、こうしたリスクを正しく理解したうえで、外国人従業員に対し「毅然と断ること」「必要に応じて警察や入管に相談すること」など、適切な対応を促す指導と周知を徹底することが求められる。