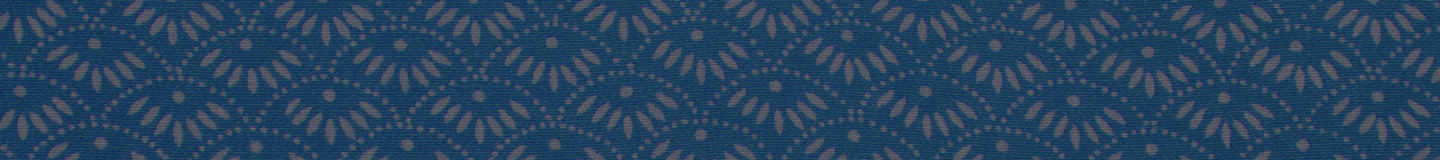外資による都心不動産の活発な取得動向
近年、東京都心部の不動産市場では、外国人投資家による購入が急増している。都心6区(千代田・港・中央など)では、70㎡あたり1億6000万円を超える築浅の高級物件に、外資の買い注文が集中している。欧米やアジアの富裕層は、銀座・赤坂・虎ノ門などの一等地に位置する高級レジデンスを購入し、資産保全や賃貸収益を目的とした投資を行っている。外資系の不動産仲介会社によれば、2024年下半期には月間50件以上の契約が成立しており、短期転売や賃貸運用を前提とした取引が拡大しているという。
こうした動きの背景には、東京オリンピック後の再開発による都市機能の向上や、円安による日本不動産の割安感がある。東京の不動産は、政治的・経済的に安定した環境のもと、「安全資産」としての魅力を高めており、世界中の投資家から注目を集めている。この状況を受けて、国土交通省は2025年に初めて外国人による不動産購入の実態調査を開始した。約11万件の登記情報をもとに、地域別・時系列で外国人投資の動向を分析し、今後の住宅政策や市場健全化に向けた基礎資料とする方針である。
外国人投資家にとっての東京都内不動産の魅力
日本は世界的に見ても政治・経済の安定性が高く、OECD(経済協力開発機構)の評価でも最上位に位置づけられている。これにより、カントリーリスクが低く、長期的な資産保有に適した環境が整っている。政情不安や急激な制度変更による資産価値の下落といったリスクが少ないことは、投資家にとって大きな安心材料となる。さらに、日本では外国人による不動産購入に対する法的な制限がほとんど存在しない。土地付き物件や中古マンションなど、日本人と同様の条件で物件を取得可能であり、これは他国と比較して大きな優位性となる。例えば、シンガポールやオーストラリアでは外国人の土地購入に制限があるが、日本ではそのような規制がないため、参入障壁が極めて低い。
価格面でも、東京の不動産は香港やニューヨーク、ロンドンなどの主要都市と比べて割安とされている。さらに、都心部では賃貸需要が非常に高く、空室リスクが低いため、安定した賃貸収益が期待できる。とくに港区や渋谷区、中央区などでは、外国人駐在員や富裕層による高級物件の需要が根強く、利回りの面でも魅力的だ。東京は、世界的に評価される都市ブランドを持ち、交通・医療・教育などのインフラが高度に整備されている。これらの要素が複合的に作用することで、東京都内の不動産は外国人投資家にとって「安全性」「収益性」「参入のしやすさ」を兼ね備えた理想的な投資先となっている。
昭和の不動産熱とは違う令和の不動産バブル
1980年代後半、日本は空前の好景気に沸き、株式市場とともに不動産市場も急激に膨張した。地価は実体経済を大きく上回るペースで上昇し、とくに東京の都心部では「土地の値段は絶対に下がらない」という「土地神話」が広がっていた。この時期、日本企業は国内外で積極的な不動産投資を行い、ニューヨークのロックフェラーセンターやハワイのモアナ・サーフライダーやシェラトンワイキキなど、海外資産の買収も相次いだ。一方で、海外投資家も日本の商業施設やオフィスビルに注目し始めていた。
バブル期の特徴は、低金利政策による余剰資金が不動産市場に流れ込み、地価が異常に高騰したことが挙げられる。資産価格の上昇は金融機関の融資拡大を促し、投資が加速する「金融と不動産の連鎖」が生んだ。しかし1990年以降、日銀の金融引き締め政策により金利が上昇し、融資が抑制されたことで地下は急落。バブルは崩壊し、多くの企業や個人が巨額の不良債権を抱えることとなった。
一方、令和時代の不動産市場は、好景気による過熱ではなく、供給不足・資材高騰・円安・海外資金の流入といった複合的な要因で価格が上昇している。都心6区では坪単価1000万円を超える新築マンションも登場し、一般的な所得層では手が届かない水準に達している。昭和期では全国的に地価が上昇したが、現在は都市部と地方で価格の「二極化」や「三極化」が進行。都市部では上昇傾向が続く一方、地方では空き家問題が深刻化し、価格が下落または無価値化している地域もある。
また、昭和期は国内資金が中心だったが、現在は海外ファンドや外国人投資家の資金が市場を動かす重要な要素となっている。円安の影響で日本の不動産が割安に見えることも、外資流入を加速させている。昭和バブル期は「過剰な楽観と金融緩和」による熱狂だったのに対し、現在の市場は「構造的な供給不足とグローバル資金の流れ」によって形成された、より複雑で選別的な局面にあると言える。
外国人による不動産取得と安全保障上の問題
近年、日本国内で外国人や外資系企業による不動産取得が増加する中で、安全保障上の懸念が浮上している。とくに、自衛隊基地や原子力発電所、国境離島などの重要施設周辺の土地が外資に取得されるケースが報道され、国会でも問題視されるようになった。こうした背景を受け、政府は2022年に「重要土地等調査規制法」を施行した。この法律により、重要施設や国境離島の周辺を「注視区域」や「特別注視区域」に指定し、土地の所有者や利用目的の調査、事前届出制度などを導入した。違反者には刑事罰が科される可能性もある。
ただし、この法律の適用範囲は限定的であり、都市部や観光地などの規制対象外の地域では依然として外資による自由な土地取得が可能である。たとえば、北海道のニセコ町では、外国資本による森林取得が進み、私有林の約4.5%が外資に保有されているという調査結果もある。さらに、法人名義での取得や第三者名義を通じた取引により、実質的な所有者が不透明なケースも多く、制度的な課題が残されている。日本には法人の背後にいる「実質的所有者(UBO)」を把握する制度が整っておらず、資本の流れを追跡する仕組みが不十分とされている。
こうした状況は、単なる経済問題にとどまらず、水源地や農地などの戦略的資源の保全にも関わるため、今後の法整備や情報の透明化が求められる。外国人投資家による不動産取得は、経済活性化の一因であると同時に、制度的・安全保障上の課題も孕んでいる。今後は、透明性の高いルール整備と地域特性に応じた政策対応を通じて、日本の不動産市場はより持続可能で信頼性の高い投資先として進化していくことが期待される。