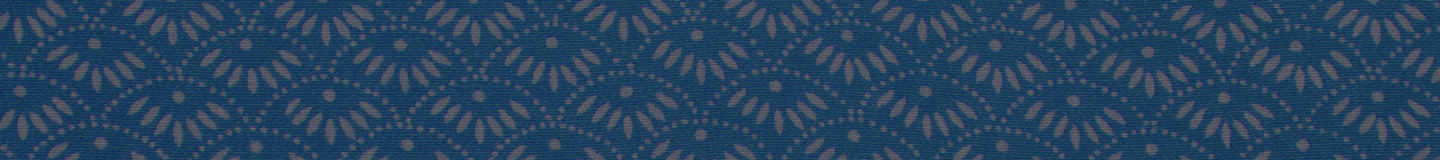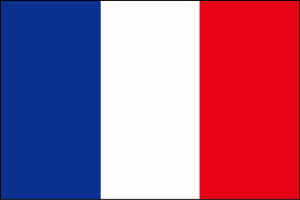
フランス特派員 大貫麻奈
フランスでの生活において避けて通れないのが『ストライキ』。とくにヨーロッパでは交通機関のストライキが頻繁に発生し、鉄道から航空会社まであらゆる公共交通機関が止まり、身動きが取れなくなることもある。どれほど大事な予定があろうとも、ストライキが行われている間は決して動くことはない。それは人々に大きな影響を与え、自分たちの要求を認めてもらうためである。一方で、日本ではストライキはあまり馴染みがなく、2023年にそごう・西武で行われたストライキは、大手百貨店として61年ぶりの出来事であり、大きく報道された。
タイトルにある『Grève』とは何か。実はフランスではストライキのことを『grève(グレーヴ)』と呼ぶ。この言葉はパリ市庁舎と深い関係があり、市庁舎前にあるパリ市庁舎広場は、かつての『place de la grève(グレーヴ広場)』に由来している。この『grève』は『砂』を意味し、セーヌ川右岸に位置するこの広場は砂地に囲まれ、かつて船の主要な停泊地の一つであった。当時、多くの失業者がこのグレーヴ広場に集まり、荷物の積み下ろしなどの仕事を探していた。この歴史から、現在でもストライキのことを『グレーヴ』と呼ぶようになった。

この広場はクリスマスマーケットやオリンピックの会場として利用されたが、かつては死刑が執行される場所でもあった。最初の処刑は1310年に行われ、1792年には初めてギロチンによる処刑が実施された。1832年以降、死刑執行は別の場所へ移されたが、それまでの長い間、この広場は公開処刑の場として恐れられていた。
では、なぜフランスはこれほどまでにストライキが多い国になったのか。ストライキが正式に認められたのは意外にも第二次世界大戦後のことであり、それまでは法律で禁止されていた。フランス革命直後の1791年に制定された法律では、結社が禁止されており(現在ではストライキの禁止と解釈されている)、この法律は1884年まで効力を持っていた。しかし、共和政と王政が繰り返される中で、徐々にストライキが認められるようになった。
20世紀に入ると、全面的に認められてはいなかったものの、ストライキの回数は増加した。とくに大きな影響を与えたのが1936年6月の『grève générale(ゼネスト)』であり、これにより年間12日の有給休暇と週40時間勤務を義務付ける法律が制定された。また、労働時間の短縮は長年にわたるストライキの主要な目的となっており、1889年には5月1日を毎年ストライキの日と定めた。この日は現在でも『メーデー(la fête du travail)』と呼ばれる祝日となっている。
このように、フランスではストライキを通じて自らの要求を訴え、生活や労働環境の改善を目指してきた歴史がある。しかし、日常生活に支障を来すストライキが発生することも珍しくない。
2023年には、年金受給年齢の引き上げに反発したごみ収集や焼却場の従業員がストライキを行い、パリを悲惨なゴミの山にしてしまった。また、オリンピックの開会式に合わせた交通機関の大規模ストライキや、エッフェル塔の職員によるストで閉鎖されるなどの出来事もあった。

当初は、どうして自国の評判を下げるような行動を取るのか疑問に感じていた。しかし、前述の通り、ストライキではインパクトが重要であり、多くの人々に大きな影響を与えることが必要不可欠なのである。そのため、とくに交通機関のストライキはヴァカンスの時期に多く見られる。もちろん、交通機関だけでなく、教育機関や医療機関でもストライキが実施されることがある。
ストライキ期間中のフランス人は、もちろんストレスを感じることもあるだろうが、何とか乗り切る方法を模索し、柔軟に対応している姿が見られる。文句を言いに行くのかと思いきや、逆にこの状況を楽しむような気持ちで行動している人々を見ると、こうした柔軟さの大切さに気づかされる。
ストライキはあらかじめ日程が予告されるため、パリを訪れる際は事前に情報を確認し、ストライキが予定されている場合にはそれに備えて行動することが重要である。運悪くストライキの日に当たったとしても、普段は味わえない体験ができたり、予想外の場所を訪れることができたりと、新たな発見があるかもしれない。ただし、デモが行われている場所には近づかないよう注意が必要である。
フランス人のように上手く『Grève』と向き合うことができれば、より一層パリを楽しむことができるだろう。