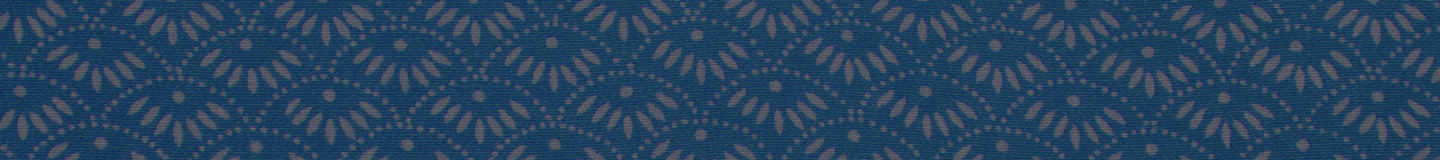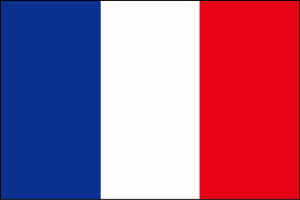
フランス特派員 大貫麻奈
日本にいても一度は耳にしたことがあるであろう「ノートルダム大聖堂」。「Notre-Dame(ノートルダム)」は”我らの貴婦人”と訳され、聖母マリアを指す。つまりノートルダム大聖堂は聖母マリアに捧げられた教会なのである。パリのノートルダム大聖堂が有名だが、この名前は他の都市にある大聖堂にも使われており、例えばストラスブールやランスにあるノートルダム大聖堂など、多くのフランス語圏の都市に存在する。
パリのノートルダム大聖堂は、パリ始まりの地と言われる「シテ島」(パリの中心部を流れるセーヌ川の中洲)に位置する。1163年に建設が開始され、100年以上もの長い年月を経て、1272年に完成した。1991年にはパリのセーヌ河岸地区としてユネスコの世界遺産に登録され、ゴシック建築の傑作として知られている。
ノートルダム大聖堂は、カトリック教徒に限らず多くの人々にとって祈りと心の拠り所となっている。しかし、2019年4月15日に大聖堂で発生した大規模な火災は、多くの人々にとって衝撃的な出来事であった。人々は大聖堂の周りでひざまずきながらアヴェ・マリアを歌い鎮火を願ったとされているが、尖塔は焼け落ち、周辺の屋根は崩落してしまった。
大規模な火災後、ノートルダム大聖堂の修復工事が開始され、2000人を超える作業員と250社の企業が参加した。彼らは、現在の技術ではなく、当初の材料と技術を用いて修復を進めることで、以前のノートルダム大聖堂を取り戻そうとした。この努力にはフランス人の熱意が込められており、ノートルダム大聖堂が彼らにとっていかに重要な存在であるかが窺い知れる。
.png)
大聖堂内にあるパイプオルガンの修復も大変なものであった。このオルガンの調律師として長年携わってきた関口格さんは、火災後の修復作業に重要な役割を果たした。火災による大きな損傷は避けられたものの、8000本ものパイプの解体と洗浄、そして繊細な音色の調整が必要であり、関口さんはこの非常に大変で重要な作業を担当した。
この大規模な工事は5年間にわたり、12月7日に再開記念セレモニーが行われた。12月8 日から再び一般公開が始まったが、工事は一般公開後も2026年まで継続される予定だ。来場者は火災前の1000~1200万人を上回ると予想されている。入場料は無料だが、しばらくは予約が必要である。
この壮大な大聖堂を元通りに修復する作業は、きっと計り知れない苦労と困難が伴ったはずである。しかし、パリに戻ってきたノートルダム大聖堂は、再び多くの人々にとって心の拠り所となり、ぜひ訪れたい場所になることだろう。
.png)