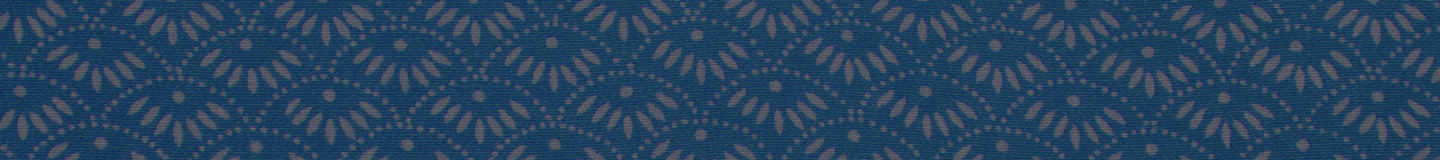メキシコ特派員 鯨岡繁
「日本とメキシコ」の漢字表記は「日墨」です。「墨」がメキシコだとご存じでしたか? 昭和30年増補版の「字源」には中国語表記の「墨」が有って、「スミ」の説明の後に、国名(墨西哥・メキシコの略称)と続きます。未検証ですが、ネット検索でメキシコの漢字表記を探すと、「女喜志古」と「墨期矢哥」も出て来ます。明治時代に中国語表記の「墨西哥」が正式に採用されましたが、中国式の「墨」ではなく、日本式に「墨」との事です。
太古より現代に至る、日本とメキシコの見えざる往来
メキシコシティ(以下「CDMX」と記述します)では、日墨協会とか日墨会館は今も立派に活動をしています。日本メキシコ学院 (Liceo Mexicano Japones, AC)と称す学校がCDMXに存在し、別名日墨学院で通じますが、日本人も殆どリセオ(LICEO)と呼びます。ラテンアメリカのスペイン語ではLICEOは小・中学校を意味し、メキシコ人コースも併存する事からLICEOが主流なのかと思います。最近の人物往来として、女優・歌手の上白石萌音さんと萌歌さんの姉妹がLICEOに数年間在席していました。彼女らのお父様が、文科省の派遣教員として鹿児島県から派遣されたLICEOの先生でした。シシド・カフカさんはメキシコ生まれの日本人芸術家でありますね。
さあ、歴史をずっと遡りましょう。氷河期まで戻ると、今から約2万年以上前にベーリング陸橋を渡ってアジアからアメリカ大陸へ人類が移動しました。そこまで戻るの?と自問自答をしました。「日本とメキシコの往来」という視点では、この大移動は直接的な交流とは見做されないので、「古代にアジアから人類がアメリカ大陸へ渡ったが、メキシコに関して交流は無かった」と言うのが一般の認識でしょう。但し、太古の昔に今のメキシコの地へ日本の文化を携えて辿り着いた民族が居たに違いない、と私は勝手に感じています。

メキシコのオアハカ州にて毎年7月の第3と第4月曜日に開催される、現地語 (サポテコ語)で「共有する」や「捧げる」という意味の「ゲラゲッツァア」と称する、地域の先住民文化を祝う歌と踊りの祭典があります。もう20年以上も昔の事ですが、歌と踊りを観客席で楽しんでいた時、何と私が子供時代に育った宮城県の「まつしーまーのさーよーずいがんじーほーどの」と言う歌詞の「斎太郎節(大漁唄い込み)」のメロディーが聞こえ(た様に)感じました。踊り手の女性の服装はスペイン風でしたが、私の耳に響いたメロディーは何と松島の民謡でした。(写真は、メキシコ初の女性大統領、クラウディア・シャインバウム氏のインスタから)
日本とメキシコの人物往来を探して歴史を彷徨うと、豊臣秀吉の名前が出て来ました。豊臣秀吉がメキシコと直接に関係したのではなく、秀吉が発したキリシタン禁教令に依って、宣教師6名・パウロ三木ら日本人20名が大阪・京都などで捕えられ、1597年2月5日(慶長元年12月19日)に長崎・西坂の地で処刑されました。その殉教者の一人がフランシスコ会のフェリーペ・デ・ヘスス修道士で、メキシコ人でありました。殉教者達は「西坂の丘」が、キリストが十字架に架けられたエルサレムの「ゴルゴタの丘」に似ていることから、この地を処刑の場に願い出たのだと言われています。何と悲しい人物往来でしょう。

殉教者26人の等身大と言われるブロンズ像の内、右側から13番目がフェリーペ・デ・ヘスス修道士との事です。背丈が低いのは少年殉教者です。この教会は聖フィリッポ教会と命名されています。メキシコ人フェリーペの名前のイタリア語読み。
長崎市西坂町に在ります二十六聖人教会の記念碑。
2023年11月12日に筆者が撮影
フェリーペは若くしてフランシスコ会に入会しますが、すぐに還俗してしまいました。 その後フィリピンへ渡り、理由は不明ですが、マニラで再びフランシスコ会に入会しました。 二度目の修道会での生活では真面目に日課をこなし、そのお蔭で修道士名を与えられました。しかし、当時マニラには叙階式をおこなう司祭が滞在しておらず、生国メキシコへの一時帰国が許されることになります。その際乗船した船が遭難し、日本漂着、殉教(1597年)という運命を辿ったのです。(滋賀大学・川田玲子先生執筆、WASEDA RILAS JOURNAL NO.8 P341-P345、「日本で殉教した(1597年)メキシコ人フェリーペ・デ・ヘスス」)
日産自動車は会社再建の為に、国内では追浜工場と湘南工場を閉鎖しますが、メキシコでは発祥の地であるCIVAC工場(モレロス州・クエルナヴァカ市)を2026年3月に閉鎖する事を発表しています。このクエルナヴァカ市には荘厳で美しいカテドラルが有り、フランシスコ会修道院の修復作業中に、内部壁面下に長崎26聖人殉教の情景を描いたフレスコ画が石灰で塗り込められていたのが1961年に発見されました。フレスコ画は今も保存されています。それらの一つに、フェリーペ・デ・ヘスス修道士の言葉と絵が描かれており、小職の記憶に間違いが無ければ「¡AH! TAIKOSAMA」と読めました。このフェリーペ・デ・ヘスス修道士が日本・メキシコの往来人物の最初の人ではないでしょうか。CIVAC工場に関してはニッサンサニーのメキシコ版の「TSURU」と「TSUBAME」に触れない訳にはゆきませんが、それは別途話題にしたいと思います。
徳川家康とメキシコを結んだ海難史
次は、徳川家康の時代になります。フィリピン・マニラからヌエバ・エスパーニャ(メキシコ)のアカプルコへ向かっていたスペイン船サン・フランシスコ号が、台風により現在の千葉県御宿沖で1609年9月30日(慶長14年8月11日)に座礁しました。その季節は丁度台風の通過が多いですね。この時、乗員約370名のうち300名以上が御宿の海女さんや大多喜藩によって救助されたと伝えられています。不幸な難破ですがホッとする話です。


JR御宿駅のプラットフォームに在る海女さん像
その後、船長ドン・ロドリゴ(フィリピン総督代理)一行は江戸に赴き、徳川家康にも謁見しました。船長の出生地がメキシコ・プエブラ州テカマチャルコだったため、御宿町はテカマチャルコ市と姉妹都市契約を調印。更に、航路上の重要港であったアカプルコとの関係を記念し、御宿町はゲレーロ州のアカプルコ市とも姉妹都市になっています。
既にキリスト教の弾圧が始まっていましたが、1613年10月28日 (慶長18年9月15日)には、伊達政宗の命を受けて支倉常長ら慶長遣欧使節の一行が西洋式帆船「サン・ファン・バウティスタ号」で(現在の)石巻市月浦を出港しました。約三か月の航海を経て翌年1月28日にアカプルコに上陸し、そこから徒歩や馬でCDMXに向かい同年3月24日に辿り着きました。筆者は駐在時代の休暇時には自分で運転してアカプルコへ行きましたが、標高差が2200メートル有り、逆ルートのアカプルコからCDMXへは全部が登りの道なき道で、それを如何様に進んだのか想像を絶します。
その一行がCDMXで宿泊した宿が今はSANBORNSというレストランの本店になっており、「青いタイルの家」として超有名な観光名所です。CDMXでは副王や大司教に謁見した記録が残っています。一行は同年5月8日にCDMXを出発し、大西洋岸の港町のヴェラクルスへ徒歩や馬で陸路移動し、ヴェラクルスにて帆船を手に入れて同年6月10日に出港しました。キューバのハバナ港からスペインのセビリア港を経てローマへ至り教皇パウロ5世に拝謁しました。一行の復路はアカプルコからマニラ経由で1620年に帰国しましたが、帰国後はキリスト教禁止令下で幕府から冷遇され、支倉常長は1622年7月1日に逝去。享年52歳。「日本人がローマを訪問して帰国する為に、メキシコの太平洋側と大西洋側とを陸路で横断・往復した最初の事実」は、メキシコに関与する筆者にとり不滅の歴史であります。

逆ルートのアカプルコからCDMX

榎本武揚とメキシコの名もなき人々
最後に、明治初期の移民計画に触れます。明治政府は海外移民を模索したそうです。それが、函館五稜郭にて新政府軍と戦った幕臣の榎本武揚が、後に明治政府の一員になった事は歴史の綾でしょうが、榎本武揚が遂行した最初の公式な日本人移民団がメキシコ南部チアパス州に1897年に到着しています。しかし現地の準備不足や農業条件の厳しさにより、多くが苦難に直面。生き残った一部の移民はアメリカへ移動しました。これは「日本人移民の苦難の先駆け」として記録されています。非常に興味深いのは、筆者がこの25年間にメキシコビジネスに携わってメキシコ各地で新たに名刺交換をした時に、そのメキシコ人の苗字の中に日本の姓が入っている事が有りました。若い方は何世にもなっていると思われますので榎本移民団の末裔とは思えませんが、所謂移民日系の方ではなく、完全にメキシコ人社会で育ち、自分には日本の血が流れていると話題にされたことが何度もあります。
メキシコではフルネームは本人の名前+父方の姓+母方の姓と並びますが、いずれかの姓に明らかに日本人の姓と分かる方に何度か遭遇しました。これは正に、庶民の日墨人物往来と常に感激を覚える次第です。