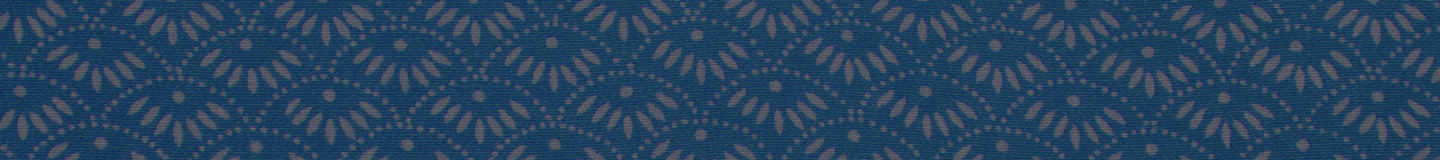中国特派員 斉海龍
年末年始が近づくと、中国でも日本でも帰省して家族と過ごす習慣がある。家に帰れば、家族が忙しく美味しい料理を用意してくれる。そこで、今回の記事では日中両国の食文化の違いについて、自分の観察や考えを共有したいと思う。
食文化とは、地域、民族、集団などが共有し、固められた様式として習慣化され、伝承された食べ物に関する食をめぐる文化の総称である。
-4.jpg)
.jpg)
(1)食材の選択
日本における食材の種類については、海産物はもちろん、米や野菜を中心に作られた料理が多いようである。日本はユーラシア大陸の東に位置し、環太平洋火山帯の一部であり、主に日本列島、南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島などの弧状列島により構成され、海に囲まれた島国である。そのため、豊かな海洋資源に恵まれ、季節感や新鮮さを大切にしている。例えば正月の御節料理では、それぞれの料理に吉祥を表す意味が込められている。
日本における食材の種類については、海産物はもちろん、米や野菜を中心に調理された料理が多いようである。日本はユーラシア大陸の東に位置し、環太平洋火山帯の一部であり、主に日本列島、南西諸島、伊豆諸島、小笠原諸島などの弧状列島から成る、海に囲まれた島国である。そのため、豊かな海洋資源に恵まれ、季節感や新鮮さを重視している。
中国の食材の種類は大きく3つに分かれる。北の地域では小麦、南の地域では米が主食とされている。また、地理的にはアジア大陸の東、太平洋の西に位置し、沿岸部では海産物が多く使用される。現行の地理区分は東北、華北、華南、中南、西南、西北の6つに分かれており、広大な面積を持つため、地域によって食習慣や風習が多様である。中国では豊かさや多様性を重視し、とくにお祝いの際には、鶏肉、魚、肉類などさまざまな料理が用意され、富や円満を象徴する傾向がある。
(2) 調味料の特徴
日本料理の調味料として最初に思い浮かぶのは味噌である。多くの日本の飲食店では、注文後にまず味噌汁が提供される。また、ねぎ、塩、シソ、昆布、ソース、マヨネーズ、酢、からし、唐辛子、乳製品(チーズ、バター、牛乳)などもよく使われている。
中国料理の調味料は多種多様であり、よく使われるものには塩、醤油、砂糖、味の素、オイスターソース、唐辛子、山椒、胡椒、料理酒、にんにく、ごま油、片栗粉などがある。また、マージョー、ローリュ、八角、桂皮、サンザシなど、さまざまな香辛料も使用されている。
調味料の使い方から見ると、日本では食材本来の味が重視され、味の濃い調味料はあまり好まれないようである。一方、中国では味の濃い食材(例えば、肉の臭みなど)を覆い隠すために調味料が多用されている。要するに、日本では味の軽い調味料が好まれるのに対し、中国では味の濃い調味料が好まれる傾向にある。
(3) 調理法
料理を作る上で最も重要なのは調理法である。新鮮な食材であっても、調理法が悪ければ、うまみが引き出されない。
日本料理には「五法」と呼ばれる調理法があり、これは揚げる、生食、蒸す、焼く、煮るの五つの基本調理法を指す。
一方、中国料理の代表的な調理法には、煎る、炒める、揚げる、炊く、蒸す、にがり、燻す、煮るなどがある。
これらの調理法が両国の国民に与える影響について考えると、日本はあっさりとした味付けを好み、食物本来の味を楽しむ習慣が根付いている。例えば、日本の平均寿命(男女)は世界で最も長く、WHO(世界保健機関)が発表した2023年版の世界保健統計によると、平均寿命(男女)は84.3歳である。男女別では、男性はスイスが81.8歳、女性は日本が86.9歳でそれぞれ1位である。日本の男性は81.5歳で2位となっているが、スイスとはわずか0.3歳の差である。このことからも、日本の生活や食生活が健康に直結していると言える。
一方、中国の飲食文化は数千年の歴史を持ち、時代と共に進化し、料理も少しずつ改善されてきた。「山に頼りに山を食う、水を頼りに水を飲む」ということわざがあり、広範な地域でさまざまな料理が生み出されている。これらは、ふるさとが異なる人々にとって重要なコミュニケーション手段となっている。
中華料理にせよ、日本料理にせよ、地理的条件や習慣によって料理は多様であり、独自の特徴と魅力を持っている。日常生活で異国の料理を試しながら、食文化の違いを楽しむことができるのも一興である。